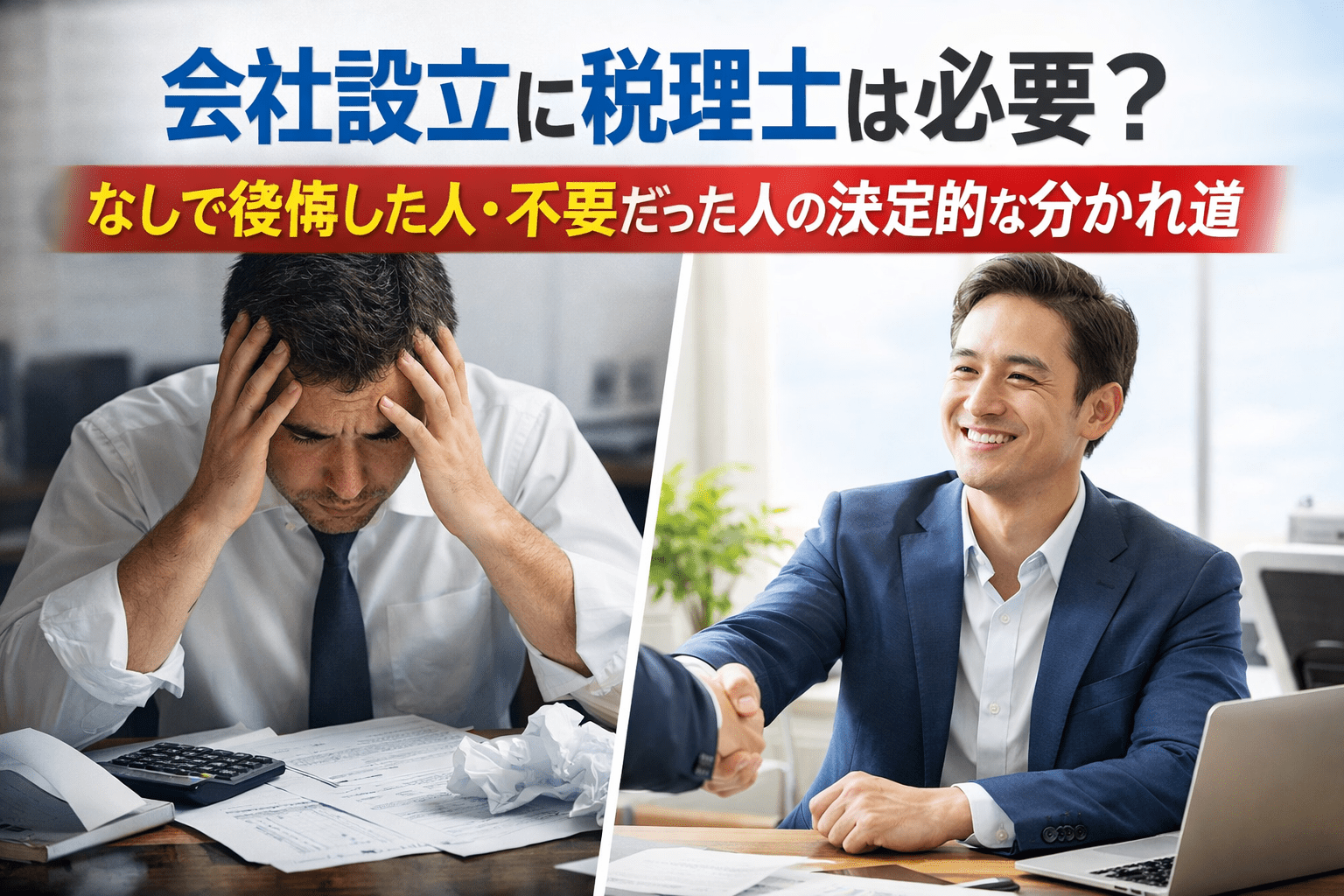
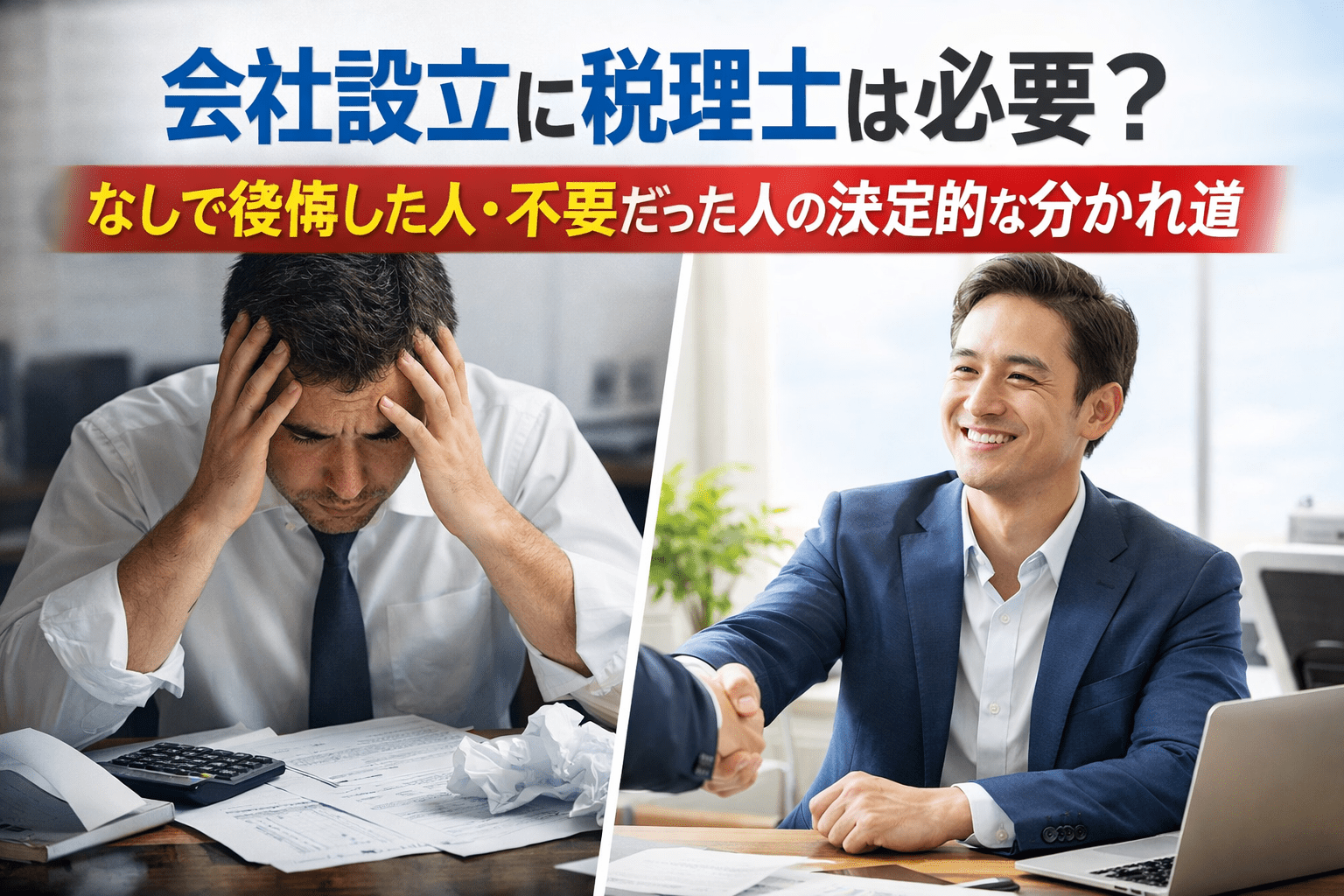
本ページはプロモーションが含まれています。
会社設立に税理士は必要?なしで後悔した人・不要だった人の決定的な分かれ道
結論から言うと、会社設立に税理士が必要かどうかは「人による」というのが現実です。
実際には、
- 税理士を付けずに取り返しのつかない失敗をした人
- 税理士なしでも問題なく進められた人
が、はっきり分かれます。
よく聞かれるのが、
- 青色申告を逃した
- 役員報酬の設定ミスで税金が増えた
- 創業融資で門前払いされた
といったケースです。
これらはすべて、「設立時の判断ミス」が原因です。
この記事では、
- 会社設立で税理士が必要な人・不要な人の明確な判断基準
- 税理士なしで後悔しやすい具体例と失敗パターン
- 依頼する場合の費用相場と注意点
- 「結局どうすればいいか」の現実的な答え
を、初めて会社を作る方でも判断できるように解説します。
会社設立に税理士は必要?まず知っておくべき前提
法律上、税理士は必須ではない
まず大前提として、会社設立に税理士は法律上必須ではありません。
登記は司法書士(または自分)で行えますし、税務署への届出も書類自体は誰でも提出できます。
そのためネット上では、
「会社設立に税理士は不要」
という意見も多く見かけます。
ただし問題は、「できる」と「失敗しない」は別という点です。
税理士なしで会社設立して後悔しやすい人の特徴
ここが最も重要な判断ポイントです。
① 創業融資を受ける予定がある人
創業時に日本政策金融公庫などの融資を検討している場合、税理士の有無で結果が大きく変わります。
- 事業計画書の完成度
- 数字の整合性
- 金融機関からの信頼性
これらは独学で作ると高確率で突っ込まれるポイントです。
- 税理士関与あり → 面談がスムーズに進む
- 税理士なし → 書類差し戻し・追加説明を求められる
というケースは珍しくありません。
② 税務・会計がよく分からない人
「会計ソフトがあれば何とかなる」と思われがちですが、
- 役員報酬の決め方
- 消費税の判断
- 経費にできる・できないの線引き
は、設立初年度の判断が数年間影響します。
ここを間違えると、
- 税金が毎年高くなる
- 修正申告が必要になる
といった事態になりがちです。
③ 本業に集中したい人
起業直後は、
- 営業
- 集客
- 商品・サービス作り
に時間を使うべき時期です。
税務や会計に時間を取られることで、 本来得られたはずの売上を逃すケースも多く見られます。
税理士なしでも問題なく進められる人の特徴
一方で、次のような人は税理士なしでも大きな問題は起きにくいです。
① 融資を使わず、シンプルな事業から始める人
- 自己資金のみ
- 売上・取引先が少ない
- 消費税の判断が単純
このような場合は、会計ソフト+最低限の知識でも対応できる可能性があります。
② 税務・会計の実務経験がある人
- 経理経験がある
- 個人事業主として確定申告を問題なくしてきた
こうした方であれば、法人化しても対応できるケースがあります。
ただし、この場合でも**「設立時だけスポットで相談する」**という選択肢は検討する価値があります。
会社設立時に税理士をつけるメリット
税務上の致命的なミスを防げる
設立時には、
- 青色申告承認申請
- 各種届出の期限
- 消費税の選択
など、一度ミスすると取り返しがつかない判断が集中します。
税理士をつける最大の価値は、 **「後戻りできない失敗を防ぐこと」**です。
融資・資金調達で有利になることが多い
税理士が関与しているだけで、 金融機関からの見え方は大きく変わります。
「数字の裏付けがある」「第三者がチェックしている」 という安心感は、融資の世界では非常に重要です。
長期的な節税につながる
- 資本金の設定
- 役員報酬の金額
- 社会保険とのバランス
これらは設立時の判断が、その後ずっと影響します。
税理士費用以上の差が出ることも珍しくありません。
実際に「税理士なし」で会社設立した人の失敗パターン
ここからは、ネット上の体験談や相談事例でよく見かける**「税理士を付けずに会社設立した結果、後悔につながったパターン」**を紹介します。
青色申告を逃してしまったケース
副業から法人化したある起業家は、「会社を作れば節税できる」と考え、設立後しばらく税理士を付けませんでした。
しかし実際には、
- 青色申告承認申請書の提出期限を知らなかった
- 設立後すぐに出すべき書類を後回しにしていた
その結果、初年度は青色申告が使えず、
- 欠損金の繰越ができない
- 本来使えた節税特例がすべて使えない
という状態に。
なぜこうなったのか:
青色申告承認申請書は、設立から3ヶ月以内(または最初の事業年度終了日のいずれか早い日)に提出する必要があります。
この期限を知らなかったこと、そして「後で調べればいい」と先送りしたことが原因です。
どうすれば防げたか:
設立時に税理士またはスポット相談を利用していれば、必要な届出と期限をリスト化してもらえます。
この1回の相談があるだけで、数年にわたる節税機会の損失を防げました。
役員報酬の設定ミスで税金が増えたケース
ある経営者は会社設立時、
- 「役員報酬は後から自由に変えられる」
- 「利益が出てから考えればいい」
と勘違いしていました。
その結果、
- 設立直後に高めの役員報酬を設定
- 業績が悪化しても変更できず
法人税+個人の所得税・住民税が同時に重くなる状況に。
役員報酬は、
- 原則として期首に決めた金額を1年間固定
- 途中変更すると損金算入できない
というルールがあります。
なぜこうなったのか:
「役員報酬は自由に変えられる」という誤解と、事業計画と報酬額のバランスを考えずに決めてしまったことが原因です。
結果として、売上が想定より少なくても高い役員報酬を払い続ける必要が生じました。
どうすれば防げたか:
税理士に相談していれば、事業計画に基づいた適切な役員報酬額の設定、社会保険料とのバランス、年間の税負担シミュレーションなどを事前に行えます。
この「最初の設定」が1年間、場合によっては数年間の税負担を左右します。
融資で門前払いされたケース
日本政策金融公庫の創業融資に挑戦したある起業家は、
- 事業計画書を自己流で作成
- 数字の根拠が曖昧
- 役員報酬・資金繰りの説明が弱い
という状態で面談に臨み、融資を受けられない結果に。
なぜこうなったのか:
金融機関が重視するポイント(返済可能性、数字の整合性、資金繰り計画)を理解せずに書類を作成したためです。
「事業への熱意」は伝わっても、「返せる根拠」が示せませんでした。
どうすれば防げたか:
創業支援に強い税理士であれば、金融機関が見るポイントを踏まえた事業計画書の作成、面談での想定質問への準備、数字の裏付け資料の整備などをサポートできます。
融資の成否は、事業の立ち上がりスピードに大きく影響します。
失敗例を踏まえた結論|あなたは税理士を付けるべきか?
ここまで紹介した失敗パターンを踏まえると、判断基準はかなりシンプルです。
次の項目に1つでも当てはまるなら、設立時点で税理士を付けるべきです。
- 創業融資(日本政策金融公庫・制度融資など)を検討している
- 税務や会計に強い苦手意識がある
- 役員報酬や節税の考え方がよく分からない
- 本業に集中したい、調べ物に時間を使いたくない
これらはすべて、実際に後悔した人たちに共通していたポイントです。
一方で、
- 融資を使わず
- シンプルな事業内容で
- 会計・税務の知識や経験がある
という人であれば、税理士なし+必要なタイミングでスポット相談という選択肢も現実的です。
重要なのは、
「後から何とかすればいい」
と考えないことです。
会社設立まわりの判断は、後から修正できないものが想像以上に多いためです。
会社設立で税理士にかかる費用相場
設立サポート費用
- 目安:3万円〜10万円前後
- 顧問契約を前提に、無料または格安になるケースも多いです。
顧問契約の月額
- 小規模法人:2万円〜3万円程度
- 売上増加に応じて上昇
- 記帳代行を含めるかどうかで金額は変わります。
税理士選びで失敗しないためのポイント
創業支援・融資実績があるか
- 「税理士なら誰でも同じ」ではありません。
- 特に会社設立では、 創業支援に慣れているかどうかが非常に重要です。
料金説明が明確か
- 何にいくらかかるのか
- 追加費用の条件
- を曖昧にしない税理士を選びましょう。
相性・説明の分かりやすさ
- 専門用語を並べるだけの税理士より、 素人にも噛み砕いて説明できる人の方が安心です。
税理士を探す現実的な方法
税理士探しでよくある失敗は、
- 知人の紹介だけで即決する
- 比較せずに1人に決めてしまう
ことです。
特に会社設立では、「創業支援に強いかどうか」で差が出ます。
方法① 直接探す
- 地域の税理士事務所に問い合わせ
- ホームページで創業支援実績を確認
- 初回相談で相性を確認
方法② 商工会議所・商工会の相談窓口
- 無料または低額で相談可能
- 創業支援に慣れた専門家を紹介してもらえる
- ただし、継続的なサポートは別途契約が必要
方法③ 税理士紹介サービスを利用する
- 創業支援・融資に強い税理士を複数比較できる
- 合わなければ断りを代行してもらえる
- 初回面談は無料のケースが多い
税理士紹介サービスの中では、「税理士ドットコム」が利用者数も多く、「まだ顧問を決めるか迷っている段階」でも使いやすいという声があります。
創業期に強い税理士が多く登録されているため、「自分は税理士が必要かどうか」を確認する目的で、設立前に1人だけ話を聞いてみるという使い方でも価値があります。
※ただし、顧問料を最安値で探したい人には合わない場合もあるため、必ず複数人と比較しましょう。
よくある質問(FAQ)|会社設立と税理士の必要性
Q. 会社設立だけなら税理士はいらない?
A.法律上は不要です。ただし、
- 青色申告
- 役員報酬の決定
- 消費税・融資の判断
など、後から修正できないポイントが多いため、設立時だけでも税理士に相談する人は多いです。
Q. 会社設立後、途中から税理士を付けても問題ない?
A.付けること自体は可能です。
ただし、
- 設立初年度の判断ミス
- 提出期限切れ
は後から取り戻せません。
「後から付けるつもり」が一番リスクが高い選択肢です。
Q. 売上が少ないうちは税理士なしでも大丈夫?
A.売上の大小よりも、
- 融資を使うか
- 会計・税務の知識があるか
の方が重要です。
売上が少なくても、判断ミスで数十万円単位の差が出ることは珍しくありません。
Q. 税理士に相談したら必ず顧問契約しないといけない?
A.いいえ。スポット相談のみの対応をしている税理士もいますし、税理士紹介サービスを使えば、
- 面談のみ
- 相性が合わなければ断る
ことも可能です。
Q. 会計ソフトのサポートだけでは不十分?
A.freeeやマネーフォワードなどの会計ソフトには充実したサポートがありますが、
- 個別の税務判断
- 節税対策の設計
- 融資対応
といった部分は、やはり税理士の専門領域です。
ソフトと税理士を併用するのが理想的です。
まとめ|会社設立で後悔しないために
会社設立に税理士が必要かどうかは、
- 事業内容
- 融資の有無
- 自分の知識と経験
によって変わります。
ただし一つだけ確実に言えるのは、
「よく分からないけど、何とかなるだろう」
という判断が、 一番後悔につながりやすいということです。
少しでも不安があるなら、 設立前に一度だけ専門家に相談する。
それだけで、
- 無駄な税金
- 融資の失敗
- 初年度からのつまずき
を避けられる可能性が高くなります。
会社設立はやり直しがききません。
最初の判断を、軽く考えないことが何より重要です。