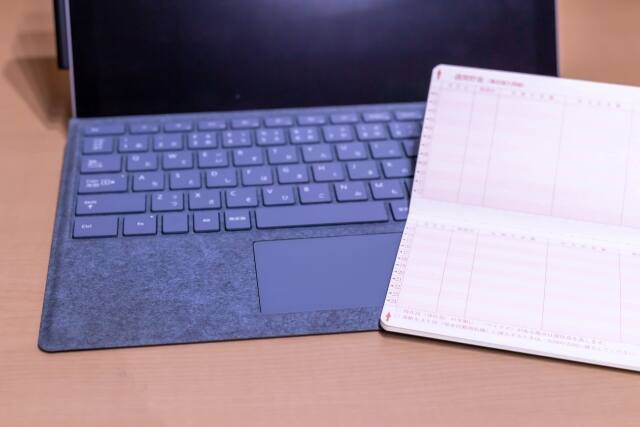
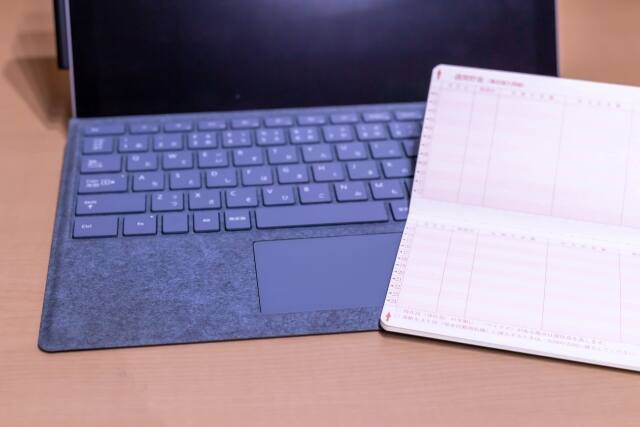
本ページはプロモーションが含まれています。
法人決算 自分で 税理士なしでもできる?初心者向け完全ガイド
「法人決算を自分で税理士なしでやりたいけど、本当に可能なの?」
多くの経営者が抱えるこの疑問に、本記事では明確な答えを提示します。
税理士なしで法人決算を行うための具体的な手順、必要なツール、押さえるべきリスクまで、初心者目線でわかりやすく解説。
コスト削減を実現しつつ、適切な決算処理を行うための実践的なノウハウをお届けします!
法人決算を自分で税理士なしで行う前に知るべきこと
税理士なしで法人決算に挑戦する前に、まず理解しておくべき基礎知識と判断基準を整理します。
法人決算とは?基本を理解する
法人決算とは、1年間の会社の経営成績と財務状態を計算し、税務署に申告するための一連のプロセスです。
具体的には以下の書類作成が必要です:
- 貸借対照表:会社の資産・負債・純資産の状況を示す
- 損益計算書:1年間の収益と費用、最終的な利益を示す
- 株主資本等変動計算書:純資産の変動を記録
- 法人税申告書:税額を計算し税務署に提出
これらの書類は会社法および法人税法により作成が義務付けられており、期限内に提出しなければなりません。
税理士なしで法人決算は可能か?現実的な判断基準
結論から言えば、シンプルな事業形態であれば税理士なしでも可能です。
ただし、以下の条件を満たしているかが重要な判断ポイントとなります:
税理士なしで対応しやすいケース
- 売上規模が年間3,000万円以下
- 従業員が5名以下の小規模事業
- 取引内容がシンプル(単一事業)
- 不動産や有価証券などの複雑な資産がない
- 経営者自身が簿記3級程度の知識を持っている
- 時間的余裕がある(年間50時間以上の作業時間を確保可能)
頼を検討すべきケース
- 売上規模が年間3,000万円を超える
- 複数の事業を展開している
- 在庫管理が複雑
- 不動産投資や有価証券運用を行っている
- 過去に税務調査で指摘を受けたことがある
- 本業に集中したい
法人決算を自分で税理士なしで行うメリット・デメリット
税理士なしで進める選択には、明確なメリットとリスクの両面があります。
両者を正確に理解して判断しましょう。
税理士なしで行う3つの大きなメリット
1. コスト削減効果が絶大
最も大きなメリットは年間20万円〜60万円のコスト削減です。
| 費用項目 | 税理士なし | 税理士依頼 |
|---|---|---|
| 月額顧問料 | 0円 | 2万〜5万円 |
| 決算料 | 0円 | 10万〜50万円 |
| 会計ソフト | 年間2万〜4万円 | (含まれる場合も) |
| 年間合計 | 2万〜4万円 | 25万〜70万円 |
特に創業期や利益が少ない段階では、この差額が経営に大きく影響します。
2. 経営数字への理解が深まる
自分で仕訳を入力し、試算表を作成する過程で、リアルタイムに会社の財務状況を把握できるようになります。
これにより:
- キャッシュフローの動きが感覚的に理解できる
- 経費削減のポイントが見えてくる
- 利益が出るタイミングを予測しやすくなる
- 融資交渉時に数字の根拠を説明できる
3. タイムリーな経営判断が可能
税理士とのやり取りを待たずに、即座に財務データを確認できます。
月次決算を自分で行えば、経営判断のスピードが格段に上がります。
税理士なしで進める際の4つのリスク
1. 税務ミスによるペナルティリスク
最も注意すべきは税務申告のミスです。
誤った申告は以下のペナルティを招きます:
- 過少申告加算税:追加税額の10〜15%
- 延滞税:年率最大14.6%
- 重加算税:悪質と判断されれば35〜40%
2. 膨大な時間投資が必要
初年度は特に学習時間を含めて年間80〜100時間の作業時間が必要です:
- 会計ソフトの習得:20〜30時間
- 日々の記帳作業:月5〜10時間
- 決算整理仕訳:15〜20時間
- 法人税申告書作成:20〜30時間
3. 節税機会の損失
税理士なしでは、専門的な節税策を見逃す可能性があります。
例えば:
- 中小企業投資促進税制の活用
- 繰越欠損金の最適活用
- 役員報酬の最適設定
- 消費税の納税方式選択
これらを見逃すと、結果的に税理士費用以上の損失となる場合もあります。
4. 税務調査時の対応力不足
税務調査が入った際、税理士なしでは適切な説明や交渉が困難です。
調査官の質問に正確に答えられないと、不利な結果を招く可能性があります。
法人決算を自分で税理士なしで行う具体的手順
ここからは、税理士なしで法人決算を進めるための実践的なステップを解説します。
ステップ1:会計ソフトの導入と初期設定
税理士なしで法人決算を行うには、会計ソフトの導入が必須です。
手書きでの対応は現実的ではありません。
初心者におすすめの会計ソフト3選
■ freee(フリー)
- 特徴:簿記知識がなくても使える直感的な操作性
- 料金:年間23,760円〜(ミニマムプラン)
- おすすめ:簿記を学んだことがない初心者
- 強み:銀行・クレカ自動連携、スマホアプリ対応
■ 弥生会計オンライン
- 特徴:老舗の安心感と充実したサポート体制
- 料金:初年度無料〜(セルフプラン)
- おすすめ:電話サポートを重視する方
- 強み:画面がシンプルで分かりやすい
■ マネーフォワードクラウド
- 特徴:金融機関連携の精度が高い
- 料金:年間35,760円〜(スモールビジネス)
- おすすめ:複数の銀行口座・カードを使い分けている方
- 強み:キャッシュフロー管理が秀逸
迷ったらfreeeがおすすめ:簿記知識ゼロでも使えるため、税理士なしで進める初心者に最適です。
まずは無料体験で操作感を確認しましょう。
ステップ2:日々の取引を記帳する
決算をスムーズに進めるには、日常的な記帳が最重要です。
【記帳の基本ルール】
- 週1回以上のペースで記帳する(溜めると大変)
- 銀行口座・クレジットカードを会計ソフトに自動連携
- 現金取引はレシートを必ず保管し、撮影機能を活用
- 勘定科目は迷ったら会計ソフトの推奨に従う
- 不明な取引は「メモ」機能で記録しておく
ステップ3:決算整理仕訳を行う
期末(決算日)には、通常の記帳とは別に決算整理仕訳が必要です。
【主な決算整理項目】
① 減価償却費の計上
パソコンや車両などの固定資産は、使用年数に応じて費用化します。
会計ソフトが自動計算してくれる場合がほとんどです。
② 棚卸資産の計上
在庫商品がある場合は、期末時点の在庫金額を計算し、「期末棚卸高」として計上します。
③ 未払費用・前払費用の整理
決算日をまたぐ費用(家賃、保険料など)を適切に按分します。
④ 売掛金・買掛金の確認
未回収の売上や未払いの仕入れを正確に計上します。
ステップ4:決算書を作成する
決算整理仕訳が完了したら、会計ソフトで自動的に決算書が作成されます。
【作成される主な書類】
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表
これらの書類に明らかな異常値(マイナスの資産など)がないか、必ず確認してください。
ステップ5:株主総会を開催し承認を得る
作成した決算書は、株主総会で承認を受ける必要があります。
【株主総会のポイント】
- 決算日から3ヶ月以内に開催
- 一人会社でも議事録作成が必要
- 議事録のひな形は法務局サイトで入手可能
ステップ6:法人税申告書を作成・提出する
最大の難関が法人税申告書の作成です。
【法人税申告で必要な主な書類】
- 法人税申告書(別表一〜別表十六など)
- 決算報告書
- 勘定科目内訳明細書
- 法人事業概況説明書
注意:法人税申告書は会計ソフトだけでは完全に作成できない部分があります。
特に別表の記入には税務知識が必要です。
国税庁の「e-Tax」を利用すると、一部が自動計算されて便利です。
ステップ7:納税を完了する
申告書を提出したら、期限内に納税します。
- 法人税:申告期限と同日
- 地方法人税:法人税とセット
- 法人住民税・事業税:都道府県・市区町村へ
- 消費税:課税事業者の場合
納付方法は、e-Taxダイレクト納付、インターネットバンキング、窓口納付などが選べます。
それでも不安な方へ:税理士を賢く活用する選択肢
「自分でやってみたいけど、やはり不安…」という方には、部分的に税理士を活用する方法もあります。
スポット契約という選択肢
日常的な記帳は自分で行い、決算時だけ税理士にチェックを依頼する「スポット契約」なら、コストを抑えつつ安心感も得られます。
【スポット契約の相場】
- 決算申告のみ:5万円〜15万円
- 記帳代行込み:10万円〜25万円
- 税務相談(単発):1万円〜3万円/回
年間顧問契約(25万〜70万円)と比べると、大幅にコストを削減できます。
自分に合った税理士を無料で探すなら
業界最大手の「税理士ドットコム」がおすすめです
【税理士ドットコムの6つのメリット】
- 登録税理士数7,100名以上で希望条件に合う税理士が見つかる
- 利用実績4万件突破の圧倒的な信頼性
- 上場企業運営だから安心・安全
- 紹介料完全無料で何度でも相談できる
- 70%以上の方が費用削減に成功
- 最短当日で税理士を紹介可能
「記帳は自分で、決算だけお願いしたい」などの相談もOK!
完全無料で最適な税理士をご紹介します
税理士ドットコムについてもっと知りたい方へ
→ 税理士ドットコムの評判が気になる方は
「税理士ドットコムの評判と口コミは?実際の利用者が語る真実」
で実際の利用者の声や詳細な比較を確認できます。
→ 他の税理士紹介サービスも比較したい方は
「税理士紹介サイト ランキング|1位はどこ?信頼と実績で徹底比較」
で各サービスの特徴を詳しく解説しています。
法人決算を税理士なしで成功させる3つのコツ
税理士なしで法人決算を乗り切るための実践的なノウハウをまとめました。
コツ1:最低限の税務知識を身につける
完璧な知識は不要ですが、最低限の基礎は押さえておきましょう。
【学習方法の例】
- 書籍:「小さな会社の経理・税金・会社法」(日本実業出版社)
- YouTube:税理士が発信する解説動画
- セミナー:商工会議所の無料講座
- 日商簿記3級:取得すれば基礎は十分
学習時間の目安は合計20〜30時間程度です。
コツ2:記帳を絶対に溜めない
税理士なしで最も失敗しやすいのが「記帳の放置」です。
【記帳を続けるコツ】
- 毎週金曜日の午後など、固定スケジュール化する
- 銀行・クレカの自動連携機能を最大限活用
- レシートはスマホで即撮影して廃棄
- 1ヶ月溜まったら税理士にスポット依頼する覚悟で臨む
コツ3:不明点は早めに専門家に確認する
分からないことを放置すると、後で大きな問題になります。
【無料相談を活用する】
- 税務署の相談窓口:基本的な質問は無料で答えてくれる
- 青色申告会:会員になれば記帳指導を受けられる(年会費1万円程度)
- 会計ソフトのサポート:チャットやメールで質問可能
- 税理士ドットコム:税理士への相談が無料でできる
よくある質問:法人決算を自分で税理士なしで行う場合
正直に言えば難易度は高いです。
ただし、以下を守れば対応可能性は上がります:
- すべての領収書・請求書を7年間保管
- 取引の根拠資料(契約書など)を整理
- 調査当日は落ち着いて事実だけを答える
- 分からない質問には「確認します」と答え、即答しない
それでも不安な場合は、調査が入った時点でスポットで税理士に立ち会いを依頼することも可能です(費用5万〜15万円程度)。
会計ソフトは記帳と決算書作成を自動化してくれますが、税務判断は自動化できません。
例えば以下のような判断は、会計ソフトだけでは対応できません:
- 役員報酬の最適金額設定
- 消費税の課税方式選択(原則 or 簡易)
- 特別償却や税額控除の適用判断
- 交際費と会議費の区分
シンプルな事業であれば会計ソフトで十分ですが、複雑な取引がある場合は税理士の判断が必要です。
初年度は特に慎重に判断してください。
創業初年度は以下の設定が将来に影響するため、できれば税理士に相談することをおすすめします:
- 資本金の設定(消費税の納税義務に影響)
- 役員報酬の決定(年1回しか変更できない)
- 青色申告の承認申請
- 消費税課税事業者の選択
最低でも初年度だけはスポット契約で税理士に相談し、2年目以降に自分で対応する方法も検討しましょう。
一般的には年商3,000万円以下が目安です。
ただし、取引内容がシンプルであれば年商5,000万円程度でも対応している経営者もいます。
逆に、年商1,000万円でも取引が複雑なら税理士依頼が賢明です。
売上よりも取引の複雑さで判断しましょう。
ミスの内容により以下のペナルティが課されます:
| ミスの種類 | ペナルティ |
|---|---|
| 申告期限に遅れた | 無申告加算税 15〜20% + 延滞税 |
| 税額を少なく申告した | 過少申告加算税 10〜15% |
| 意図的に隠蔽した | 重加算税 35〜40% |
| 計算ミス(善意) | 修正申告で追加納税のみ |
善意のミスであれば修正申告で対応可能ですが、悪質と判断されると重いペナルティが課されます。
不安な場合は、申告前に税理士のチェックを受けるのが安全です。
まとめ:法人決算を自分で税理士なしで行うための判断チェックリスト
法人決算を税理士なしで行うかどうかは、以下のチェックリストで判断しましょう。
✓ 税理士なしでも問題ないケース
- ☑ 年商3,000万円以下で取引がシンプル
- ☑ 簿記3級レベルの知識がある(または学ぶ意欲がある)
- ☑ 年間50時間以上を決算業務に充てられる
- ☑ 会計ソフトを使いこなせる自信がある
- ☑ コスト削減を最優先したい
- ☑ 経営数字を深く理解したい
✓ 税理士に依頼すべきケース
- ☑ 年商3,000万円超または取引が複雑
- ☑ 過去に税務調査で指摘を受けたことがある
- ☑ 本業に集中したい
- ☑ 会計・税務の知識がほとんどない
- ☑ ミスのリスクを最小限にしたい
- ☑ 節税対策を積極的に行いたい
最適な選択をするために
法人決算を税理士なしで行うことは、適切な準備と継続的な努力があれば十分可能です。
ただし、すべてを一人で抱え込む必要はありません。
- 日常的な記帳は自分で、決算チェックだけ税理士に依頼
- 初年度だけ税理士に相談し、2年目から自分で対応
- 会計ソフトのサポートや無料相談を最大限活用
このように、ハイブリッドな方法を選ぶことで、コストを抑えつつ安全性も確保できます。
まずは行動してみましょう
【税理士なしで進める方は】
今すぐ会計ソフトの無料体験を試してみましょう。
実際に触ってみることで、自分でできるかどうかの判断がつきます。
【おすすめ会計ソフト】
【税理士のサポートが必要な方は】
まずは無料で相談できる税理士ドットコムに登録し、スポット契約や顧問契約の見積もりを取ってみましょう。
あなたの会社に最適な方法で、効率的で正確な法人決算を実現しましょう!