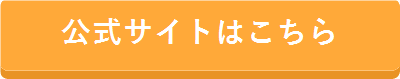本ページはプロモーションが含まれています。
一人親方の確定申告の書き方|申告書記入から提出まで完全ガイド

一人親方の確定申告の書き方を、初心者にもわかりやすく具体的に解説します。
「申告書のこの欄には何を書けばいいの?」
「どの順番で記入すればいいの?」
といった疑問を解決!
申告書の記入方法から提出手順まで、実際の書き方を画面付きで詳しく紹介します。
この記事を読めば、確定申告書の正しい書き方がすぐにわかり、迷わず申告を完了できます。
一人親方が確定申告書を書く前に知っておくべき基本
確定申告書を正しく書くためには、まず基本的な仕組みを理解することが大切です。
書き方の前に押さえておくべきポイントを確認しましょう。
確定申告書の種類と選び方
一人親方が使用する確定申告書は主に「申告書B」(現在は「申告書」に統一)です。
事業所得がある個人事業主向けの様式で、以下の特徴があります:
- 第一表: 所得金額や税額を記入するメイン部分
- 第二表: 所得の内訳や各種控除の詳細を記入
- 青色申告決算書: 青色申告者が提出する収支内訳書
白色申告の場合は「収支内訳書」を、青色申告の場合は「青色申告決算書」を併せて提出します。
どちらを選ぶかで書き方や記入項目が変わるため、事前に確認しておきましょう。
申告書作成前の準備事項
確定申告書をスムーズに書くためには、以下の情報を事前に整理しておく必要があります:
**収入に関する情報**
- 年間の総売上金額
- 取引先ごとの支払調書
- 月別の収入一覧
**経費に関する情報**
- 必要経費の合計額
- 勘定科目別の支出内訳
- 領収書や請求書の整理
**控除に関する情報**
- 社会保険料の支払額
- 生命保険料や地震保険料
- 扶養家族の情報
これらの情報が整理されていれば、申告書の記入作業がスムーズに進みます。
一人親方と個人事業主の申告書記入の違い
一人親方も個人事業主の一種ですが、申告書の書き方に特有のポイントがあります。
**業種欄の記入方法**:
- 建設業の一人親方:「建設業」
- 運送業の一人親方:「運送業」
- IT業務の一人親方:「情報サービス業」
**労災保険の特別加入**:
一人親方特有の労災保険料は、事業所得の必要経費として計上し、申告書に反映させます。
**請負と給与の区別**:
一人親方の収入は基本的に「事業所得」として申告書に記入しますが、場合によっては「給与所得」として扱われることもあるため、契約内容を確認して正しい欄に記入することが重要です。
確定申告書の具体的な書き方【記入項目別解説】
ここからは、確定申告書の実際の書き方を項目別に詳しく解説します。
記入順序に沿って、迷いやすいポイントも含めて説明します。
申告書第一表の書き方
申告書第一表は確定申告のメイン部分です。
以下の順序で記入していきます:
**1. 基本情報の記入**
- 住所・氏名・生年月日
- 職業欄:「建設業」「大工」など具体的に記入
- 屋号:個人事業主としての屋号があれば記入
**2. 収入金額等の記入**
- 「営業等」欄に事業の総収入金額を記入
- 複数の収入源がある場合は合計額を記入
- 給与収入がある場合は別途「給与」欄に記入
**3. 所得金額等の記入**
- 「営業等」欄に事業所得金額(収入-必要経費)を記入
- 青色申告特別控除がある場合は控除後の金額を記入
**4. 所得から差し引かれる金額の記入**
- 基礎控除:48万円(合計所得2,400万円以下の場合)
- 社会保険料控除:国民年金・国民健康保険料など
- 扶養控除・配偶者控除:該当する場合のみ
申告書第二表の書き方のポイント
第二表は第一表の詳細を記入する部分です:
**所得の内訳の書き方**
- 支払者の名称:取引先の会社名や個人名
- 所得の種類:「営業等」
- 支払金額:各取引先からの年間収入額
- 源泉徴収税額:源泉徴収されている場合の税額
**各種控除の詳細記入**
- 社会保険料の種類と支払額
- 生命保険料・地震保険料の詳細
- 医療費控除がある場合の明細
記入漏れが多い項目なので、証明書類を確認しながら正確に記入しましょう。
青色申告決算書の書き方
青色申告者は決算書の作成が必要です。
主なポイントは以下の通りです:
**損益計算書部分の記入**
- 売上(収入)金額:月別に記入
- 売上原価:材料費や外注費
- 経費:勘定科目ごとに合計額を記入
**貸借対照表部分の記入**
- 資産:現金、預金、売掛金など
- 負債:買掛金、未払金など
- 資本:元入金、青色申告特別控除前の所得金額
複式簿記で記帳している場合、帳簿の数字をそのまま転記します。
収支内訳書の書き方(白色申告の場合)
白色申告者は収支内訳書を作成します:
**収入の部の記入**
- 売上(収入)金額を月別に記入
- 年間合計額を確認
**支出の部の記入**
- 租税公課、荷造運賃、水道光熱費など項目別に記入
- 「その他の経費」には勘定科目名と金額を記入
**専従者給与の記入**
- 家族への給与がある場合は専用欄に記入
白色申告の場合も正確な記録に基づいて記入することが重要です。
申告書記入で迷いやすいポイントと解決法
確定申告書を書く際によくある疑問点と、その解決方法を具体的に解説します。
収入と所得の記入方法の違い
多くの一人親方が混同しやすいのが「収入」と「所得」の書き方です:
**収入(売上)の書き方**
- 年間の総売上金額をそのまま記入
- 消費税込みの金額で記入(税込経理の場合)
- 月別売上を集計して年間合計を算出
**所得の書き方**
- 収入から必要経費を差し引いた残額
- 「収入-経費=所得」で計算
- 青色申告特別控除がある場合はさらに控除
例:年間収入500万円、必要経費200万円の場合
- 収入欄:5,000,000円
- 所得欄:3,000,000円(500万円-200万円)
経費の記入で注意すべき項目
一人親方の経費記入でよくある間違いと正しい書き方:
**車両関係費の按分計算**
- 事業用と私用の区別が必要
- 事業使用割合を明確にして記入
- 例:7割事業用の場合、ガソリン代10万円×0.7=7万円を経費計上
**自宅兼事務所の按分方法**
- 床面積比で按分するのが一般的
- 家賃10万円、事務所部分20%の場合:2万円を経費計上
- 光熱費も同様の比率で按分
**交際費と会議費の区別**
- 取引先との飲食:交際費
- 打ち合わせでの茶菓代:会議費
- 金額や目的を明確に記録して記入
控除額の記入ミスを防ぐ方法
各種控除の記入で間違いやすいポイント:
**社会保険料控除**
- 国民年金保険料:控除証明書の金額をそのまま記入
- 国民健康保険料:年間支払額の合計
- 家族分も本人が支払った場合は合算可能
**基礎控除の記入**
- 2020年分以降:原則48万円
- 合計所得金額により控除額が変動
- 所得2,400万円超の場合は控除額減額
**配偶者控除・扶養控除**
- 年間合計所得金額48万円以下が条件
- 年齢や同居状況により控除額が変動
- 該当者の所得を正確に把握して記入
確定申告書作成を効率化する方法
申告書の書き方をマスターすることは重要ですが、毎年の作業負担を考えると効率化も必要です。
会計ソフトを活用した申告書作成
現在は多くの会計ソフトが確定申告書の自動作成機能を提供しています:
**主な機能**
- 日々の収支記録から申告書を自動生成
- 記入漏れや計算ミスを防止
- e-Taxでの電子申告にも対応
**おすすめの理由**
- 手書きやExcelでの管理より正確
- 税制改正にも自動対応
- 過去のデータを参照して効率的に作成
ただし、ソフトを使っても基本的な申告書の書き方を理解しておくことは重要です。
税理士による申告書作成サポート
「申告書の書き方は分かったけれど、本当にこれで合っているか不安」
「毎年の申告書作成に時間を取られすぎている」
そんな悩みを抱える一人親方の方も多いのではないでしょうか?
実は、確定申告書の作成や提出は税理士に依頼することで、大幅に負担を軽減できます。
**税理士に依頼するメリット**
- 申告書の記入ミスや計算間違いを防げる
- 節税対策を含めた最適な申告書を作成
- 税務調査のリスクを大幅に軽減
- 本業に集中する時間を確保
**「税理士ドットコム」なら無料で最適な税理士を紹介**
税理士と聞くと「料金が高そう」と思われがちですが、実際には思っているより手頃な料金で依頼できることが多いです。
「税理士ドットコム」は、税理士業界最大手の紹介サービスで、以下の特徴があります:
✅ **完全無料**で税理士を紹介
✅ 一人親方の確定申告に詳しい税理士を厳選紹介
✅ 料金体系を事前に確認できるため安心
✅ 相談後に断っても費用は一切かからない
✅ 税理士報酬を下げることに成功した利用者が7割以上
運営会社は上場企業の「弁護士ドットコム」なので、信頼性も抜群です。
**こんな一人親方の方におすすめ**
- 申告書の書き方に不安がある
- 節税対策を含めて最適化したい
- 毎年の申告作業の負担を軽減したい
- 税務調査のリスクを下げたい
まずは無料相談で、自分に合った税理士がいるかチェックしてみませんか?
\税理士ドットコムで無料相談してみる/
申告書提出の方法と注意点
確定申告書の書き方をマスターしたら、次は提出方法を確認しましょう。
e-Tax(電子申告)での提出方法
**事前準備**
1. マイナンバーカードの取得
2. ICカードリーダーライターまたはマイナンバーカード対応スマートフォンの準備
3. e-Taxの利用者識別番号の取得
**提出手順**
1. 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」にアクセス
2. マイナンバーカードでログイン
3. 作成した申告書データをアップロード
4. 電子署名を付与して送信
**e-Tax提出のメリット**
- 24時間いつでも提出可能
- 還付金の受け取りが早い(約3週間)
- 青色申告特別控除額が最大65万円
郵送・持参での提出方法
**郵送提出の場合**
- 所轄税務署宛に簡易書留で送付
- 提出期限は消印有効
- 控えが必要な場合は返信用封筒を同封
**税務署持参の場合**
- 開庁時間内(平日8:30〜17:00)に提出
- 確定申告期間中は土日も開庁する税務署あり
- 即座に受付印をもらえる
どの方法でも、提出期限(例年3月15日)を守ることが最重要です。
申告書提出後の手続き
**納税が必要な場合**
- 振替納税:指定口座から自動引き落とし
- 現金納付:金融機関や税務署で納付
- クレジットカード納付:国税クレジットカードお支払サイトを利用
**還付がある場合**
- 指定した口座に還付金が振り込まれる
- e-Tax提出の場合:約3週間
- 書面提出の場合:1〜2か月
申告書提出後も、修正が必要になった場合は「更正の請求」または「修正申告」を行うことができます。
来年の確定申告に向けた準備
今年の申告書作成が終わったら、来年に向けた準備を始めましょう。
日常的な記帳の重要性
確定申告書をスムーズに書くためには、日頃からの記帳が欠かせません:
**日次記帳のポイント**
- 収入があった日に必ず記録
- 経費の支払いは領収書と共に記録
- 月末に残高確認を実施
**月次確認の習慣**
- 売上高の前年同月比較
- 経費の予算実績対比
- 所得税の予測計算
この習慣により、次年度の申告書作成が格段に楽になります。
税制改正への対応
税制は毎年改正されるため、最新情報をチェックしておくことが重要です:
**主な確認ポイント**
- 各種控除額の変更
- 税率の改正
- 新設された制度や特例
国税庁のホームページや税理士からの情報提供を活用して、常に最新の情報を把握しておきましょう。
節税対策の計画立案
確定申告書の書き方をマスターしたら、次は節税対策を考えましょう:
**主な節税対策**
- 青色申告特別控除の活用
- 小規模企業共済への加入
- 経費の適切な計上
- 家族への給与支払い(青色事業専従者給与)
これらの対策は年間を通じて計画的に実行する必要があります。
まとめ
一人親方の確定申告書の書き方について、基本的な記入方法から提出手順まで詳しく解説しました。
**重要なポイントのおさらい**
- 申告書の種類を正しく選択する
- 収入と所得の違いを理解して正確に記入
- 各種控除を漏れなく申請する
- 経費は事業関連部分のみを適切に計上
- 提出期限を守って確実に申告
確定申告書の書き方は一度覚えてしまえば、毎年の作業がスムーズになります。
ただし、税制改正や個人の状況変化により、記入方法が変わることもあります。
「申告書の書き方は理解できたけれど、本当にこの書き方で大丈夫?」
「もっと節税できる方法はないの?」
そんな不安や疑問がある場合は、税理士に相談することをおすすめします。
税理士ドットコムなら、一人親方の確定申告に詳しい税理士を無料で紹介してもらえます。
確定申告書の書き方だけでなく、年間を通じた税務サポートを受けることで、安心して事業に専念できるでしょう。
正しい確定申告書の書き方をマスターして、一人親方としての事業をより発展させていきましょう。